今話題の動画生成AI『Sora2』の紹介とそこから見える調達業務の未来
.png&w=1920&q=75)
今回のブログでは、SNSで話題となっている動画生成AI「Sora2」を紹介します。
そして、AIの進化がこの先の調達業務にどのような変化をもたらすのかを考察していきます。
Sora2とは
OpenAIから動画生成AI Sora 2 が公開され、動画+音声の同時生成がなどが使えるようになりました。元々Soraが動画生成AIとしてOpenAIから出されていたのですが、不自然な挙動が多くありました。しかし最新モデルでは「物理法則を学習」しており、水の流れや重力、影の動きなども極めて自然です。
さらに一貫性が保たれていて、動画の初めの方に出てきたものと終盤で出てきたもので一貫した映像として成立しています。
実際に登場人物の動作や口の動き(リップシンク)も精密で、もはや実際の映像と見分けがつかないレベルに到達しています。
また、Youtubeやticktokを中心に100万回を超える再生数の動画も登場しています。そして、視聴者の多くが動画生成AIだと気づかないほどの完成度です。
https://www.tiktok.com/@h032851

実際に私も、自社サービス「スマートAI調達」のCM動画をSora2で試作してみました。
わずか数回の試行でも、かなりいいクオリティの動画が作成できました。
とはいえ、細部の演出や意図した表現まで再現するには、もう少しチューニングが必要だと感じました。
動画生成AIは、まさに言語AIがたどった進化の道を歩んでいます。
かつてGPTが文章生成の領域で飛躍的に進化し、ChatGPTの登場によって生成AIブームを巻き起こしたように、今動画や画像の世界でも「誰でも自由に作れる」時代が到来しつつあります。
以下がGoogleが出している技術論文です。興味のある方はぜひ読んでみてください。
[https://arxiv.org/abs/2509.20328]
近い将来、どんな動画や画像もAIで生成できるようになるでしょう。
その一方で、「それが本物かAIが作ったものか」 を見極めるリテラシーがこれまで以上に重要になっていきます。
フェイクニュースや誤情報を見抜く力が、AI時代の新しい教養になりそうです。
ちなみに、現在のSora2は iOSアプリ版のみ提供されています。
利用するには「招待コード」が必要で、私は運よく以下のQiita記事のコメント欄で入手できました。
現時点ではこのコードがないと使えませんが、SNS上で配布している人もいるので、そこから手に入れるのが現実的な方法です。
[https://qiita.com/7mpy/items/f56283096290a9bf0868]
Sora2から見える調達業務の未来
ここからは、Sora2のような動画生成AIが今後どのように調達業務の在り方を変えていくのかを考えてみます。
私はこれからの社内コミュニケーションは「テキスト中心」から「視覚・聴覚情報中心」へと移っていくと考えています。
例えば、上司への報告も資料を一枚一枚まとめるのではなく、AIが自動で報告用の動画を生成してくれるようになるでしょう。
AIが図やグラフを使いながら内容を読み上げる動画を数分で作ってくれる。
それを上司は移動中の車内などで視聴し、全体像をすぐに把握できます。
そして、気になった部分だけをあとで詳しくレポートで確認すればいい。
実際、私自身も似たようなことをしています。
長いPDF資料や論文を読むときは、まずNotebookLMに入れて音声読み上げで概要を把握します。
その後、チャットで質問して理解を深め、最後にファクトチェックしたい箇所だけ原文を読む。
これによって、1つの資料を読んで理解する時間が大幅に短縮されました。
[https://notebooklm.google.com/]
こうした「視覚・聴覚を活用した理解の効率化」は、すでに私たちの身近なところで始まっています。
そして今後、調達業務のような分野でも「AIが要点をまとめ、動画や音声で報告する」スタイルが当たり前になるでしょう。
わざわざ時間をかけて資料を整えるのではなく、必要な情報を最も理解しやすい形で伝える。
そんな未来が、もうすぐ目の前まで来ています。

さらに、新入社員向けの研修動画やマニュアル資料もAIが自動で作成できるようになります。
テキストを入力するだけで、AIがわかりやすくナレーション付きの動画を生成してくれる。
教育担当者が一から資料を作る必要はなくなり、更新も簡単に行えるようになります。
こうした未来は、決して遠い話ではありません。
早ければ1年以内には実用レベルで広がり始めるでしょう。
そして、私たちが開発している「スマートAI調達」でも、同じようにAIを活用した情報共有・教育の仕組みを取り入れていく予定です。
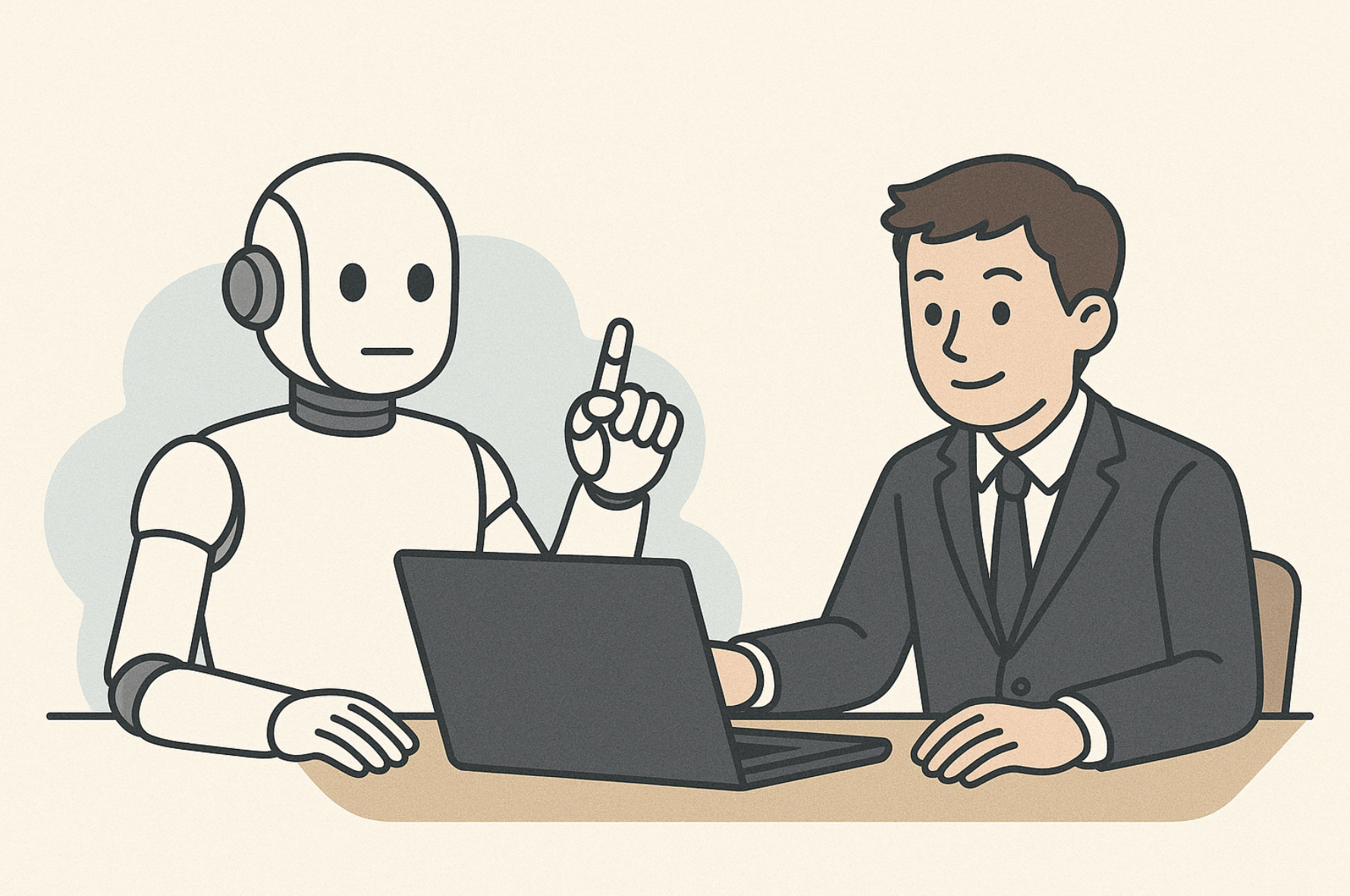
AI時代に欠かせない「データ蓄積」の重要性
AIを業務に活用する上で、絶対に忘れてはいけないことがあります。
それは 「社内データの蓄積」 です。
多くの企業では、調達の交渉履歴や見積もり比較表がメールやエクセルに点在しています。
しかし、この状態ではAIがそれらのデータにアクセスできません。
AIが使えるのは構造化され、システム上で管理されているデータだけです。
つまり、どれだけAIが進化しても、データが整っていなければ本来の力を発揮できないのです。
これは非常に重要なポイントです。
実際、AIはすでに人間の想像を超えるスピードで進化しています。
例えば図面を読み込み、人間が見落とすような設計ミスを自動で指摘できるようになっています。
いずれはAIが図面を作成し、人間がそれをレビューするだけ、という時代が来るでしょう。

ソフトウェア開発の世界では、すでにその変化が起きています。
私たちが開発している「スマートAI調達」でも、実際にタイピングして書くコードは全体の1%ほどしかありません。
ほとんどの部分はAIが生成しています。
同じような変化が、今後あらゆる業界に広がっていくはずです。
だからこそAIの恩恵を最大限に受けるためには、今のうちから業務データを AIが扱える形で蓄積 しておくことが欠かせません。
私たちが開発する「スマートAI調達」は、業務を効率化しながら日々のやり取りや見積もり情報を自動的にデータとして蓄積する仕組みを備えています。
そして、その蓄積データをAIが分析し、企業の調達力を継続的に高めるための意思決定をサポートします。
「データ×AI」によって、調達の質を一段上へと引き上げるシステムです。
[https://egghead.co.jp]
システムを導入するときのポイント
ここからは少しポジショントークになりますが、調達に限らず DXシステムを導入する際に意識してほしい大切なポイント があります。
それは「そのシステムを提供する会社がAI活用を本気で考えているか」 という点です。
他社を批判する意図はまったくありませんが、この先の未来を見据えている企業は例外なく、「AIをどのようにプロダクトに組み込むか」を真剣に考えています。
そして、多くの先進的な企業はすでにその思想を具体的な機能として形にしています。
一方で、今の時点でAIの要素がまったく見えないシステムは、今後のアップデートにもあまり期待が持てない可能性があります。
これから長く使うシステムを選ぶのであれば、「AIをどう活用していこうとしているか」 にもぜひ注目してみてください。それが、将来的にAIを使った業務効率化を大きく左右するポイントになるはずです。
参考
この記事をシェア
